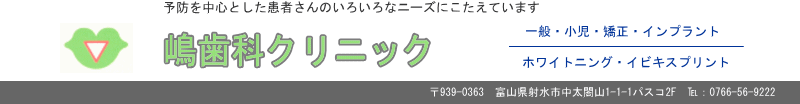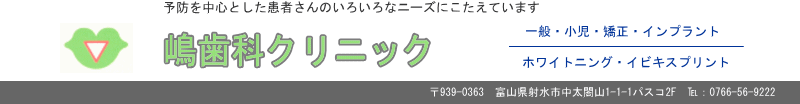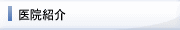
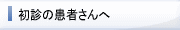
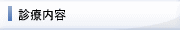
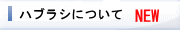
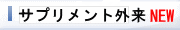
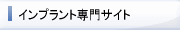
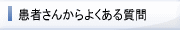
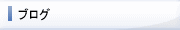
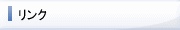
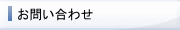
〒939-0363
富山県射水市中太閤山
1-1-1パスコ2F
TEL :
0766-56-9222
医療法人社団
嶋歯科クリニック |
|
|

|
 唾液は正常な人で一日あたり1.5~2リットルもあります。 唾液は正常な人で一日あたり1.5~2リットルもあります。
 唾液は分泌される場所は大きく分けて大唾液腺と小唾液腺に分けられ大唾液腺は耳下腺、顎下腺、舌下腺の三つがあり何かを食べるときに大量に分泌される唾液の大部分がここ(大唾液腺)から出ます。 唾液は分泌される場所は大きく分けて大唾液腺と小唾液腺に分けられ大唾液腺は耳下腺、顎下腺、舌下腺の三つがあり何かを食べるときに大量に分泌される唾液の大部分がここ(大唾液腺)から出ます。
|

 ごはんやパンなどのでんぷん質を糖に変える。(唾液中の酵素であるアミラーゼがデンプンを分解して麦芽糖に変え、吸収しやすい形にする。) ごはんやパンなどのでんぷん質を糖に変える。(唾液中の酵素であるアミラーゼがデンプンを分解して麦芽糖に変え、吸収しやすい形にする。)
 抗菌作用 唾液内にはラクトフェリン、リゾチーム、ラクトペルオキシターゼ、免疫グロブリンなどの抗菌物質を含んでおり細菌やウイルスを殺す働きがあります。 抗菌作用 唾液内にはラクトフェリン、リゾチーム、ラクトペルオキシターゼ、免疫グロブリンなどの抗菌物質を含んでおり細菌やウイルスを殺す働きがあります。
 粘膜保護作用 「粘膜保護作用」の主役となるのがムチンという物質です。ムチンはネバネバとした油状の物質で食べ物を包み込む働きを持っています。よく噛む事により唾液中のムチンが食べ物を包んで消化管をいたわる働きをします。まとめると 粘膜保護作用 「粘膜保護作用」の主役となるのがムチンという物質です。ムチンはネバネバとした油状の物質で食べ物を包み込む働きを持っています。よく噛む事により唾液中のムチンが食べ物を包んで消化管をいたわる働きをします。まとめると
胃潰瘍や胃炎の予防、改善に効果があり、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりにくくする効果があります。
 粘膜修復作用 唾液中にはEGF(Epidermal Growth Factor)という皮膚が傷ついたとき、血液や汗、唾液などを通じて供給され、傷跡を残さず修復するように作用するタンパク質が多く含まれています。またもう一つNGF(Nerve
Growth Factor). 粘膜修復作用 唾液中にはEGF(Epidermal Growth Factor)という皮膚が傷ついたとき、血液や汗、唾液などを通じて供給され、傷跡を残さず修復するように作用するタンパク質が多く含まれています。またもう一つNGF(Nerve
Growth Factor).
神経成長因という神経細胞の修復を促す作用、神経細胞の存在を維持する作用、脳の損傷を修復する作用、脳神経機能を回復し脳の老化を防ぐ物質が含まれ全身をまわるとされています。
 唾液が人間の生命活動を維持するために大変重要な働きをしていて唾液を維持し分泌を促進することがいかに重要かおわかりいただけたかと思います。 唾液が人間の生命活動を維持するために大変重要な働きをしていて唾液を維持し分泌を促進することがいかに重要かおわかりいただけたかと思います。
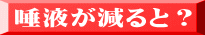
 唾液が減ったり体内の免疫力が落ちたりすることにより口腔内の常在菌の中のカンジタ菌が増えると舌が痛くなる「舌痛症」や唇の横が切れる「口角炎」になったり極端に少なくなった場合粘膜に炎症を起こしたり舌がひび割れたり舌がうろこ状になったりします。カンジタ菌が増えると舌に白い苔状(舌苔)のものが付着しますが、これはカンジタ菌の繁殖が原因です。 唾液が減ったり体内の免疫力が落ちたりすることにより口腔内の常在菌の中のカンジタ菌が増えると舌が痛くなる「舌痛症」や唇の横が切れる「口角炎」になったり極端に少なくなった場合粘膜に炎症を起こしたり舌がひび割れたり舌がうろこ状になったりします。カンジタ菌が増えると舌に白い苔状(舌苔)のものが付着しますが、これはカンジタ菌の繁殖が原因です。
 唾液の分泌が低下すると上記(抗菌作用のとこに書いた)のような抗菌物質が減るのでさまざまな感染症にかかりやすくなり口の中の感染症の虫歯や歯周病になりやすくなります。 唾液の分泌が低下すると上記(抗菌作用のとこに書いた)のような抗菌物質が減るのでさまざまな感染症にかかりやすくなり口の中の感染症の虫歯や歯周病になりやすくなります。
 風邪を引きやすくなる(鼻の鼻粘膜が乾燥してウイルスをキャッチする繊毛運動が劣る) 風邪を引きやすくなる(鼻の鼻粘膜が乾燥してウイルスをキャッチする繊毛運動が劣る)
 「接触嚥下障害」といわれる状態になり嚥下性肺炎をひきおこしやすい。 「接触嚥下障害」といわれる状態になり嚥下性肺炎をひきおこしやすい。
 味覚障害を起こしやすい。(①唾液がでないと舌にある味を感じる器官「味蕾」がこすれて無くなって平坦舌になると味が感じにくくなる。②カンジタ菌が唾液減少で異常に増えると舌が炎症を起こしが「味蕾」が障害され起こる。) 味覚障害を起こしやすい。(①唾液がでないと舌にある味を感じる器官「味蕾」がこすれて無くなって平坦舌になると味が感じにくくなる。②カンジタ菌が唾液減少で異常に増えると舌が炎症を起こしが「味蕾」が障害され起こる。)
 ドライマウス、下記のシュグレン症候群を引き起こす。 ドライマウス、下記のシュグレン症候群を引き起こす。

 目の渇きと唾液の分泌低下(ドライマウス)を主症状にする自己免疫疾患で、40~60代の更年期女性に特に多い。この患者の20%が慢性関節リュウマチを合併している場合があります。シュグレン症候群によるドライマウスは唾液腺を自分のリンパ球が攻撃してしまうために起こります。唾液腺の他の外分泌腺の涙腺、鼻腔、消火器などにも及ぶと鼻の乾燥、胃液の分泌低下による胃炎なども引き起こされ、その他の症状として全身倦怠感、発熱、皮膚の紫斑、指のしびれなどの末梢神経障害なども。 目の渇きと唾液の分泌低下(ドライマウス)を主症状にする自己免疫疾患で、40~60代の更年期女性に特に多い。この患者の20%が慢性関節リュウマチを合併している場合があります。シュグレン症候群によるドライマウスは唾液腺を自分のリンパ球が攻撃してしまうために起こります。唾液腺の他の外分泌腺の涙腺、鼻腔、消火器などにも及ぶと鼻の乾燥、胃液の分泌低下による胃炎なども引き起こされ、その他の症状として全身倦怠感、発熱、皮膚の紫斑、指のしびれなどの末梢神経障害なども。
|